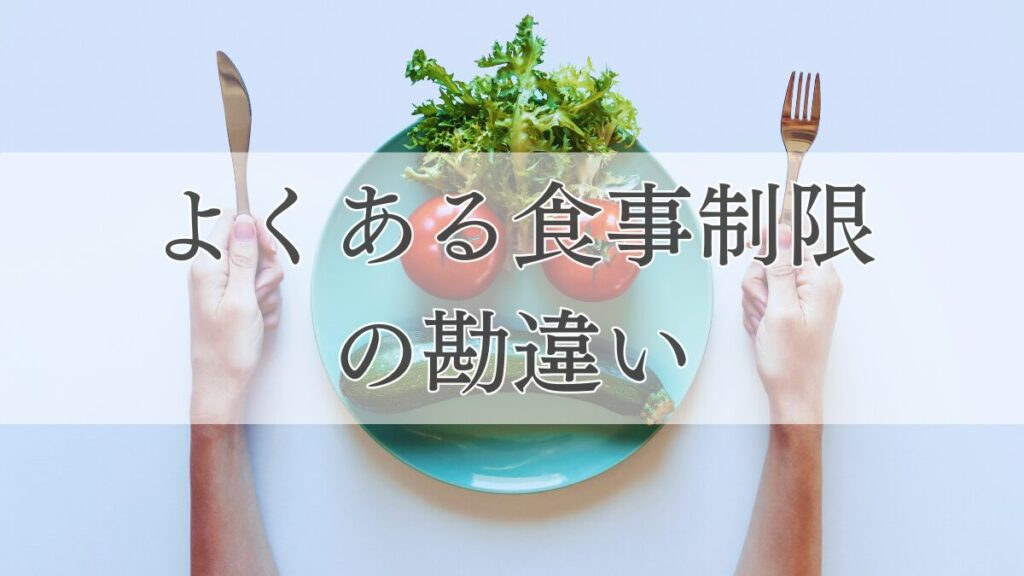
クローン病と食事制限の誤解|「食べない」より「体と対話する」食事へ
クローン病と診断されると、誰もがまず思うのが「何を食べたらいいの?」という不安ではないでしょうか。
食事制限という言葉には、「我慢」「制約」「つらい」といったネガティブな印象がつきまといます。
けれども本来、食事は心と体を整えるための自然な行為。
「食べたいものをあきらめる」ことではなく、「自分の体を理解していく」ことこそが、クローン病の食事療法の本質なのです。
この記事では、
✅ クローン病の食事制限で陥りやすい勘違い
✅ 愉しく食べるための“体との対話”のヒント
について、経験者の視点からわかりやすくお伝えしていきます。
🍞 食事制限の誤解:「好きなものは一生食べられない」?
学生の頃から食事制限をしていた私は、よくこう言われていました。
「かわいそうに」「大変そうだね」と。
笑顔で「平気だよ」と返しながらも、心の中では「本当は好きなものを食べたい」と思っていました。
ですが、のちに気づいたのです。
食事制限とは“禁止”ではなく、“調整”だということに。
食べるものを制限するのではなく、自分の体がどう反応するかを観察し、理解することが大切なのです。
つまり、我慢ではなく「体と相談しながら食べる」こと。
それが、長く安定した寛解へつながっていきます。
☕ 「悪いとわかっていても食べる」──そこに隠れた心理
私は昔から甘いものが大好きで、ストレスが溜まるとドーナツに手が伸びてしまいました。
そして、そのあとに必ず訪れる“腸の暴走”。

・ガスの発生(腸内発酵)
・頭痛(血流悪化)
・眠気(血糖値変動)
・悪寒(消化不良)
このような反応は、病気の有無に関わらず誰にでも起こります。
クローン病だからではなく、「体が今、何を負担に感じているか」を教えてくれているのです。
「食べたら悪い」ではなく、
「体がどう反応するかを知る」──
そう思えるようになると、罪悪感のない食事が増えていきます。
🍚 病気でも健康でも同じことが起きている
健康な人でも、脂質や糖分を摂りすぎれば腸内環境は乱れます。
クローン病の方は特に、腸の炎症や免疫の反応が強く出やすいため、症状が顕著になるだけのこと。
「難病だから特別」というよりも、体の反応が敏感に現れているだけなのです。
この視点に立つと、
「クローン病だから我慢する」ではなく、
「私の体は何を求めているのか」を感じ取ることができます。
🥗 「あきらめる」ではなく、「上手に付き合う」
嗜好品・外食・加工食品などを“悪”と決めつける必要はありません。
むしろ、「食べたい」と感じた背景を理解することが大切です。
・疲れて甘いものが欲しくなる
・孤独を埋めるために何かを食べたくなる
・ストレス解消の手段として食を使っている
その一つひとつに、「今の自分を整えたい」という願いが隠れています。
だから、付き合い方を変えれば、制限は「選択」になるのです。
🌿 「体に悪い」だけで終わらせない
体に悪いといわれる食べ物にも、心を癒す力があります。
たとえば、甘いものを少し口にして「ほっとする」――それも治癒反応の一つです。
食事とは、単なる栄養補給ではなく、感情の調整でもあるのです。
クローン病のように腸の不調を抱える方こそ、
“体に合う食材を知る”ことと同じくらい、「心が満たされる食事」を大切にしてほしいと思います。
🧘♀️ 食事制限は「我慢」ではなく「学び」
クローン病の食事制限を通じて、私は学びました。
それは、「食べること=自分と対話すること」だということ。
体の声を聴くようになると、腸の状態や心のバランスがつながっていることに気づきます。
食べすぎた日、焦った日、泣いた日。
そんな感情と体調のリンクを感じるたびに、「私の中で何が起きているのか」を知る手がかりになります。
🍵 食事を通して、心が育つ
クローン病とともに生きる中で、食べることは「戦い」ではなく「対話」になります。
食事制限を通して、自分の内側と向き合う力が育ちます。
食を整えることは、心を育てること。
そして心が整えば、体もまた回復へと向かう。
食の本質を見つめ直すことは、
「病気と共に生きる」ことを少しずつ“穏やか”に変えていくプロセスなのです。

🩺 さえき生薬のご案内
病気を敵とせず、身体と対話しながら生きる――
そんな新しい健康観を、日々の暮らしの中で育てていく。
さえき生薬では、東洋の叡智と心のケアを融合させ、
「整える・感じる・生きる」をテーマに、心身のバランスを取り戻すサポートを行っています。
クローン病・自己免疫疾患・精神疾患など、
医療では届きにくい“心と体の狭間”に寄り添いながら、
あなただけの回復の道を一緒に探していきます。
▶︎ 詳しくは「サービス紹介」へ
4つの安心サポート